主なご病気
コミュニケーション症群(吃音など)
知的能力・感覚障害(視覚や聴覚)・運動機能障害などが無いにも関わらず、言語・会話・コミュニケーションにおいて支障をきたすものの総称で、さらに以下のように分類します。
●言語症
言葉を理解することや言葉をまとめて話すことが生まれつき不得手であるため、語彙力が非常に少なかったり文法を理解することができず、効果的な言語的コミュニケーションを行うことができません。その結果、学業成績や社交面で著しい支障をきたします。始語が遅かったり、表出する言葉の数が少なくて気が付かれることもあります。
限局性学習症(学習障害)、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)、発達性強調運動障害(DCD)、社会的コミュニケーション症の併存がみられることがしばしばあります。
●語音症
言葉を話すための音や単語の知識、唇や舌や顎などの言葉を話すために協調的に運動する力が乏しいために、正確な言葉や文章を発することが不得手な特性です。言語症と同じように、効果的な言語的コミュニケーションや意思伝達が上手にできません。
成長により改善することも多いので、言葉を話すことに過度なプレッシャーを与えないことが重要です。
●社会的コミュニケーション症
場面や状況によって、挨拶・情報共有・話し方・相槌や合図などを調整しながらコミュニケーションを取っていますが、そのようなルールが生来的に理解できず社会的コミュニケーションに支障をきたします。
例えば、「遊び場所や教室で声の大きさや話し方を変えることができない」「相手が大人か子供かで話し方を変えることができない」「過度に堅苦しい言葉で話す」「字義どおりに受け取るなど、あいまいな表現が分からない」「相槌など非言語的コミュニケーションができない」などがあります。自閉スペクトラム症(ASD)の症状と重なりますが、社会的コミュニケーション症は行動や興味の限局性や反復性といった面はみられず、支障はコミュニケーション場面に限られます。
●小児期発症流暢症(吃音)
言葉や単語を理解する力やまとめる力はあり会話は成立するが、言葉や文章を流暢に話すことができない障害です。「音の繰り返し=吃音(どもり)」「音の引き伸ばし」「単語の途切れ」などにより対人コミュニケーションに支障をきたします。
「症状が出ることへの不安」=予期不安、「人と話すことへの恐怖」=対人緊張や社交不安症が生じることがあります。特に人前で話す際には、流暢に話すことを過剰に意識してしまうあまり、不安や緊張が強まって症状が悪化してしまうことがあります。同じように不安やストレスで生じやすいチックの併存もしばしばみられます。
また、成人時に発症する吃音は社交不安症との関連が強いと考えられます。

【治療と対策】
20人に1人の割合でみられると報告されており、比較的よくみられる症状です。6歳までに発症する患者さんが8割以上ですが、ほとんどの患者さんが青年期までには回復することが多いので、不安や緊張を取る治療を行ったり、言語訓練を受けるなど適切な治療を受けることで二次障害を生じないようにすることが重要です。
主なご病気
-

うつ病
誰もが耳にしたことがあると思われる代表的な病気です。憂鬱な気持ちや意欲が出ないことが続いていませんか?
-

双極性障害(躁うつ病)
うつ状態だけでなく、極端に調子がよくなって活発な期間がある方は躁うつ病の可能性があります。うつ病とは治療が異なるので注意が必要です。
-

統合失調症
悪口を言われる、狙われているといった幻聴や妄想などを症状とする病気です。100人に1人くらいの割合でみられます。
-

認知症
物忘れ、新しいことが覚えられない、判断力の低下などにより日常生活に支障をきたす病気です。
-

適応障害
強いストレスを受け続けると様々な心身の症状が出ることがあります。
-

自律神経失調症
自律神経(交感神経と副交感神経のバランス)が不調をきたすことで様々な心身の症状が出ることがあります。
-

不眠症
なかなか寝付けない、何度も目が覚めるなど睡眠の問題で苦しんでいませんか?
-

パニック障害
場所と時間を選ばず、突然パニック発作が生じ、日常生活に支障をきたす病気です。
-

強迫性障害
強迫観念と言われる強い不安感を打ち消すための行動により、日常生活に支障をきたす病気です。
-

身体表現性障害
いくら検査しても病気が見つからないにも関わらず身体症状が持続し、日常生活に支障をきたす病気です。
-
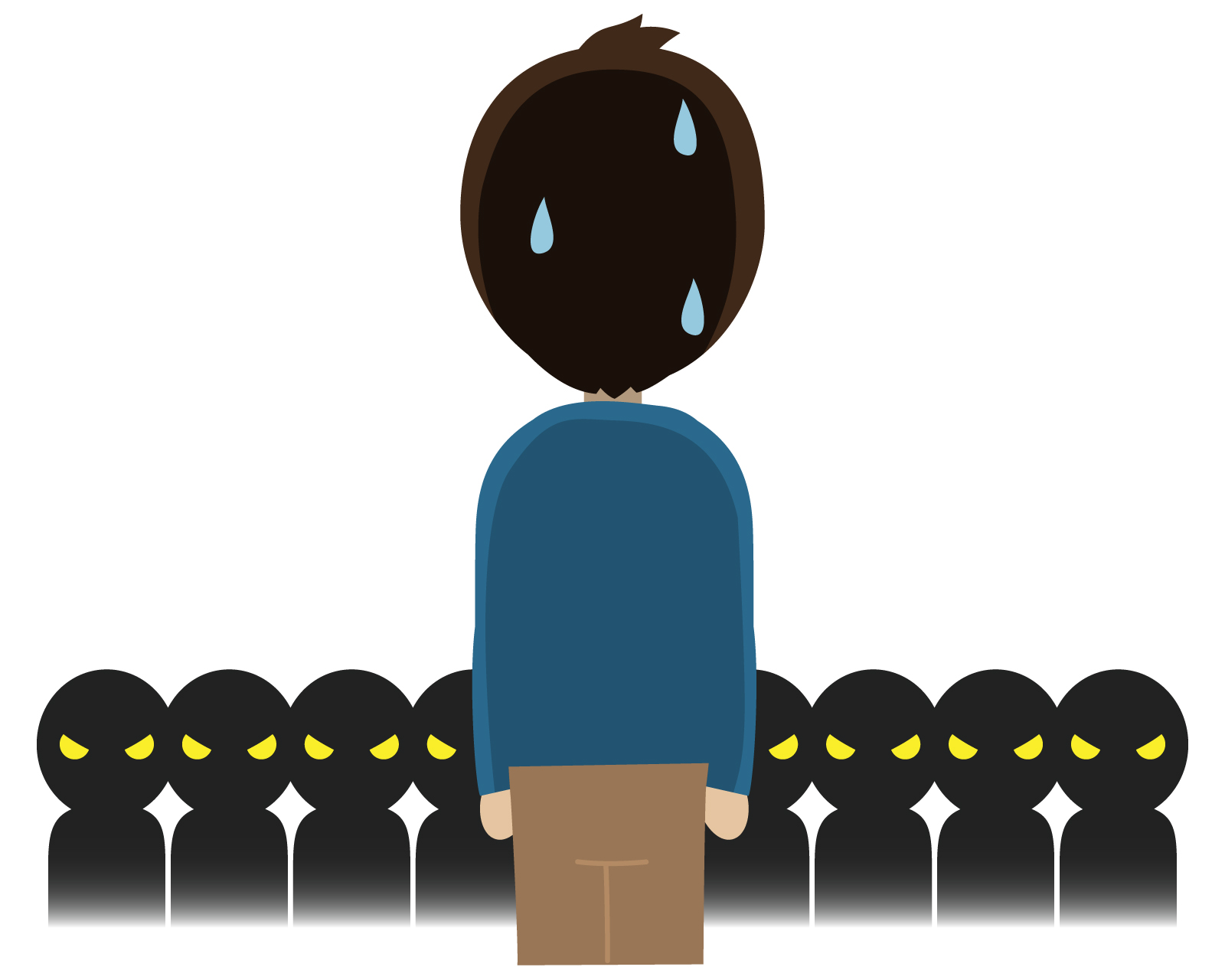
社交不安障害
会議や発表など注目を浴びる場面の時に強い不安感や身体症状が出ることで日常生活に支障をきたす病気です。
-

神経発達症(発達障害)
「生まれもった脳の機能の偏りから生じる様々な特性(個性)により、日常生活に困りごとが生じている状態です。
-
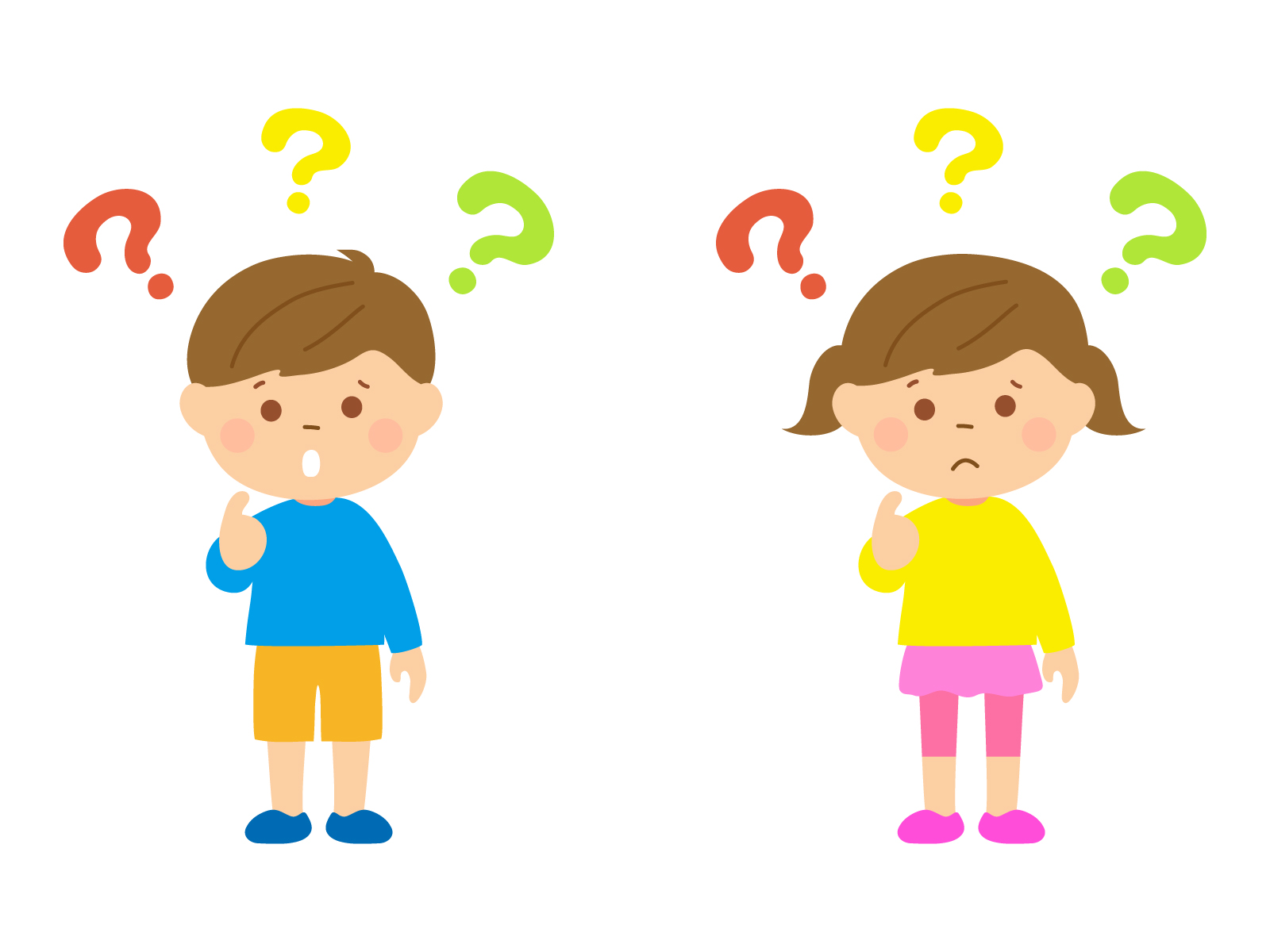
知的能力障害群
知的能力と社会生活への適応機能の遅れがあり、日常生活に困難をきたします。
-

コミュニケーション症群(吃音など)
自分の意志を伝えたり、相手の意志を伝えることが苦手で日常生活に支障をきたします。
-

自閉スペクトラム症 ASD
臨機応変な対人関係や、自分の関心・やり方・ペースが崩れることが苦手な特性を持つ発達障害のひとつです。ごく軽度から重度まで特性の程度は様々です。
-

注意欠如多動症(AD/HD)
子供では多動や衝動性が目立ち、成人では不注意症状で困る方が多いです。発達障害のひとつで、近年注目度が増している病気です。
-

学習障害(限局性学習症)
知能は正常にもかかわらず、特定の部分の学習が極端に苦手な特性をもつ発達障害のひとつです。知能が正常であるため気がつかれにくいようです。
-

運動症群
運動や動作のぎこちなさ、姿勢の乱れから日常生活に支障をきたします。
-

チック症
子どもに多く、意図せずに声が出てしまったり、不規則な動きが出てしまう病気です。
-

重ね着症候群
自閉スペクトラム症が基底障害にあり、二次障害として様々な症状や病気を生じている状態です。
-

分離不安
母親などの愛着対象から離れることに対して、年齢と不相応に強烈な不安を感じる状態です。
-

場面緘黙症(社交不安症)
家などでは普通に話すことができるのに、学校などの「特定の場面」で声を出すことができない状態が続くことです。
-

愛着障害
養育者との愛着が何らかの理由で形成されず、子どもの情緒や対人関係に問題が生じる状態です。
-

抜毛症
子どもに多く、自分で自分の毛髪を抜いてしまいます。


